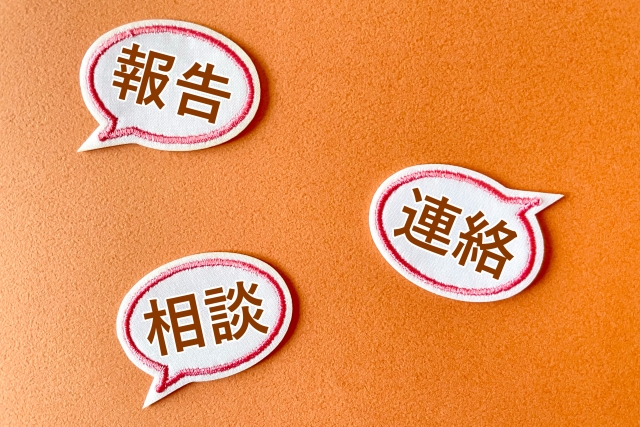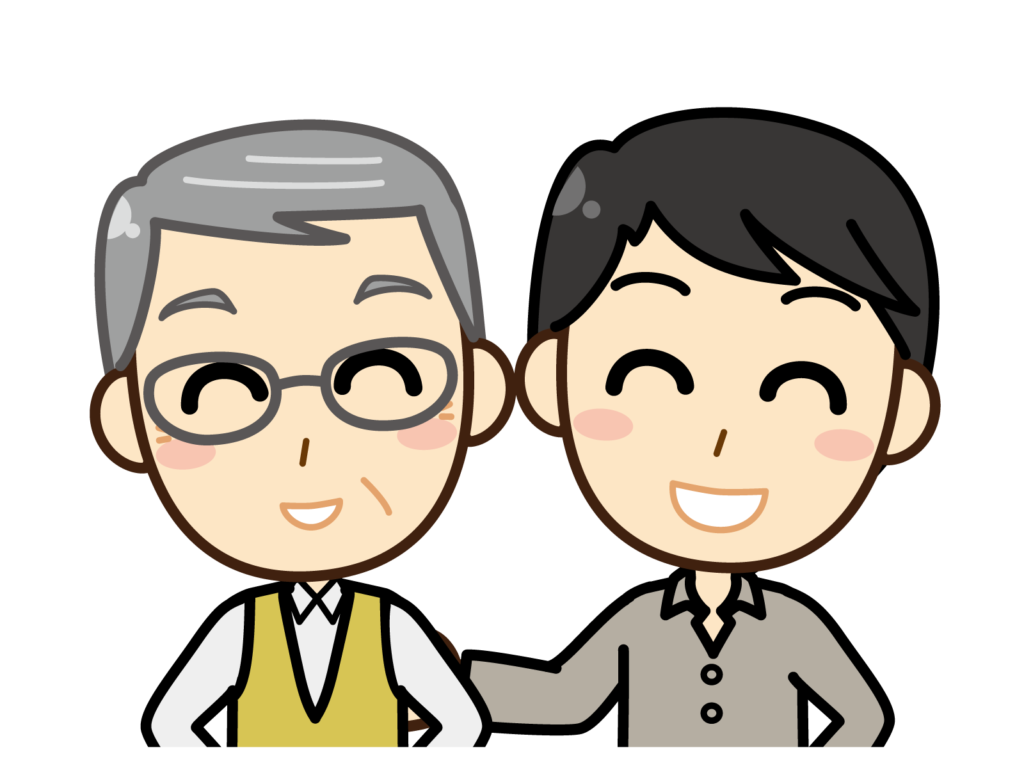法定後見について①ー3つの類型ー
●はじめに
・認知症の親がお金の管理ができなくなり、自覚もないままに莫大な額の浪費をしてしまった。
・銀行に行ってきたはずなのに、下ろした現金や印鑑、通帳が見当たらず、あちこちに連絡をとって確認することを何度もくりかえす。
・さまざまな手続きの仕方がわからず身寄りもいないので必要なサービスを結ぶことができない。
・施設入所のために定期預金を解約しなければならないのに、本人に手続きを行うことができる判断能力がない
長年、医療介護福祉の現場で働いていると、このようなケースに何度も直面することがあります。
別の記事で説明しているように、まだ判断能力がある方に関しては、判断能力が低下したときの備えとして任意後見契約を結ぶことをお勧めしておりますが、すでに判断能力が低下しており契約能力がない方に関しては、任意後見契約を結ぶことができません。
そのような方に関しては、任意後見ではなく法定後見によって後見人を選定しサポートしてもらう制度を活用します。
今回は、すでに判断能力が低下してしまっている方に対して代理人を選任しサポートする法定後見について解説していきます。
●法定後見の3つの類型
法定後見には、本人の判断能力のレベルに合わせて、以下の通り3つの類型があります。
・補助
・保佐
・後見
補助は、支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることが難しい場合がある方
保佐は、支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない方
後見は、支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない方
あくまでも目安に過ぎませんが、長谷川式簡易知能評価スケールという認知症の尺度を測る検査においては、
16〜19点:補助
11〜15点:保佐
10点未満:後見
と大別されることがあるようです。
(『成年後見の実務』公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートより)
そして、それぞれの類型において裁判所から選任されて支援する代理人を、補助人・保佐人・後見人と呼びます。
補助人・保佐人・後見人では、本人を支援する際の権限が以下のように異なります。

代理権とは、預貯金口座の解約や不動産の売買契約など財産に関わる重要な行為を本人代わって行う権限です。
同意権とは、預貯金口座の解約や不動産の売買契約など財産に関わる重要な行為を本人が行う際に、代理人の同意を必要とする権限です。
取消権とは、本人が代理人の同意をえないで行った取引や契約などを取り消すことができる権限です。
民法13条1項に定められている行為とは、以下の通りです。
・貸したお金の元本の返済を受けること
・借り入れをしたり、保証人になること
・不動産などの重要な財産について、取得したり、手放したりすること
・原告となって訴訟を起こすこと
・贈与すること、和解すること、仲裁契約を結ぶこと
・相続の承認や放棄をしたり、遺産分割をすること
・贈与や遺贈を拒否したり、負担付贈与や負担付遺贈の承諾をすること
・新築や改築、増築、大修繕を行うこと
・一定の期間を越える賃貸借契約を結ぶこと(例えば3年を超える建物の賃貸借)
●まとめ
・法定後見とは、すでに判断能力が低下してしまっている人に対して、代理人を選任しサポートする仕組みである。
・法定後見には、補助・保佐・後見の3つの類型がある。
・それぞれの代理人が有する権限が異なる
・権限には代理権・同意権・取消権がある。